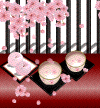遺言において、自分が死んだら相続人以外の第三者に相続財産の全部または一部を贈与することを「遺贈(いぞう)」と言います。
遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」があります。
◆特定遺贈◆
特定遺贈とは、遺産のうち特定の財産や金額を指定して贈与することを言います。
例えば、「自宅不動産を遺贈する」「金3,000万円を遺贈する」「下記土地300坪のうち100坪を遺贈する」というようなケースです。
◆包括遺贈◆
包括遺贈は、財産を具体的に特定せず、遺産の全部又はその一定割合を贈与することを言います。
例えば、「遺産のすべてを包括的に●●に遺贈する」「遺産の2分の1を包括的に××に遺贈する」というようなケースです。
包括受遺者の権利義務と相続人の権利義務の違い
遺贈を受ける人を「受遺者(じゅいしゃ)」と言い、包括遺贈を受ける者を「包括受遺者」と言います。
包括受遺者は、法律上、相続人と同一の権利義務を有すると定められています(民法第990条)が、相続人と全く同一の権利と義務を有する訳ではありません。
以下に相続人との代表的な共通点・相違点を記載します。
(1)包括受遺者は、相続人と同様に、自分が受遺者になったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対し遺贈の放棄または限定承認の申立てをしなければなりません。
なお、特定遺贈の受遺者は、いつでも遺贈の放棄をすることができ(民法第986条)、その手続きは家裁の手続きは不要で、単に遺贈義務者(相続人や遺言執行者等遺贈の履行をする義務を負う者)に対する放棄の意思表示をすれば足ります。
(2)包括受遺者は、相続人と同様に遺産分割協議に参加して、個々の遺産について、法定相続分・受遺分と異なる遺産承継の仕方を協議することができます。
その裏返しとして、包括遺贈の割合に応じて債務を承継する義務を負います。
ちなみに、特定遺贈は、遺言で特別な指定(負担付遺贈)がない限り、遺言者の負債等を引き継ぐことはありません。
(3)遺贈が効力を生じる前に包括受遺者が死亡したときは、遺贈は効力を生じません。
つまり、相続人と違い、包括受遺者の地位が代襲されることはありません。あくまで、包括受遺者は、受遺者固有の権利と考えられているからです。
なお、「包括受遺者が既に死亡している場合には、その子に包括遺贈する」旨の予備的遺言は可能ですが、この場合でも、包括遺贈の代襲という扱いではありません。
(4)相続人または他の包括受遺者が相続放棄または遺贈の放棄をした場合、放棄された相続分は、他の相続人の相続分に付加されますが、包括受遺者の受遺分には影響がありません。
(5)相続人が相続による不動産取得を第三者に対抗するには登記は必要ありませんが、包括受遺者は、登記が無い限り、第三者にその不動産に対する所有権の取得を対抗することができません。
(6)包括受遺者に対する課税は、贈与税ではなく相続税が適用されますので、他の相続人がいれば、その方と協力して遺産全体を踏まえて、申告・納税する必要があります。
特定遺贈と包括遺贈のメリット・デメリット
◆特定遺贈のメリット◆
(あ)特定遺贈の受遺者は、いつでも遺贈の放棄することができます(民法986条;前記(1)参照下さい)。
なお、いつまでも法律関係が不安定な状態におかれるのを防ぐために、特定遺贈の遺贈義務者(相続人や遺言執行者等遺贈の履行をする義務を負う者)その他の利害関係人は、相当の期間を定めて遺贈を承認するか放棄するかの意思表示を催告することができます(民法987条)。
(い)債務については、特に指定がない限り負担する義務がありません。
(う)相続人への遺贈は、不動産取得税が課税されません。
◆特定遺贈のデメリット◆
(あ)相続人以外への遺贈は、受遺者に不動産取得税が課税されます。
(い)遺留分を侵害する場合、遺留分減殺請求の対象となり、紛争が生じる可能性があります。
◆包括遺贈のメリット◆
(あ)包括受遺者は相続人と同様に遺産分割協議に参加できます。
(い)不動産取得税が課税されません。
◆包括遺贈のデメリット◆
(あ)包括受遺者は、遺贈割合に応じて債務を負担しなければなりません。
(い)遺留分を侵害する場合、遺留分減殺請求の対象となり、紛争が生じる可能性があります。