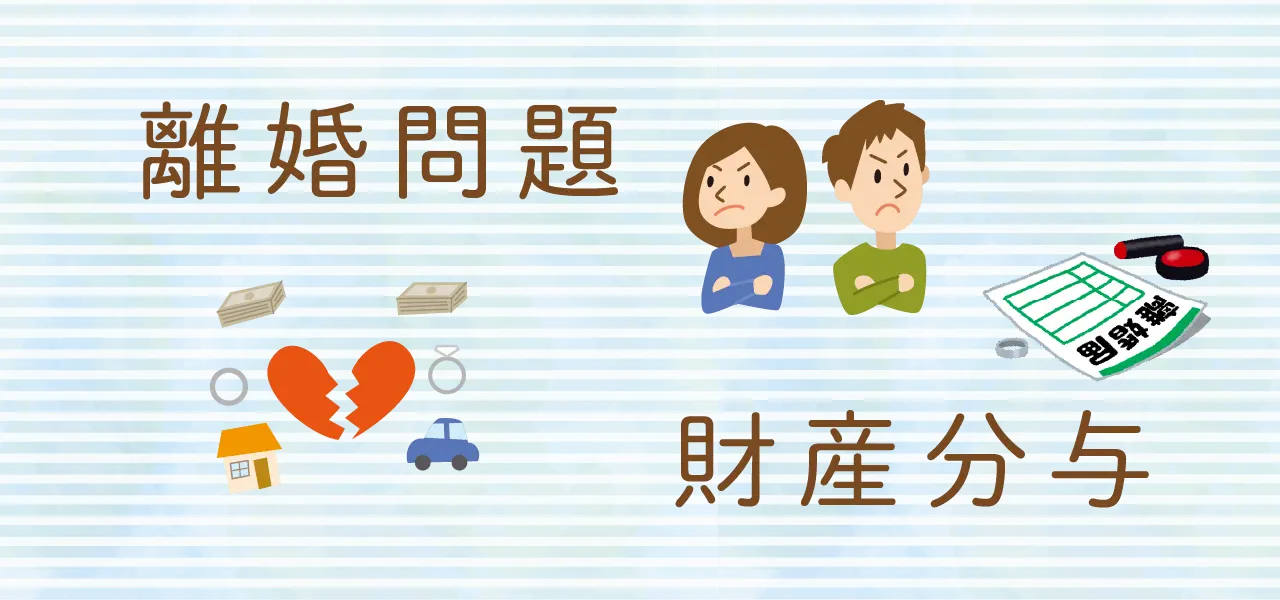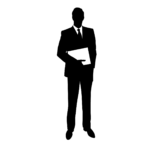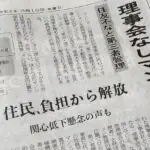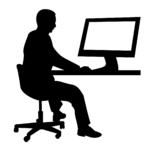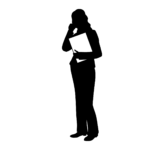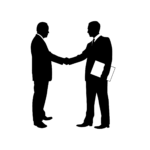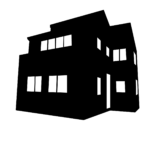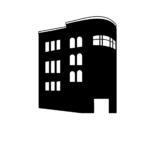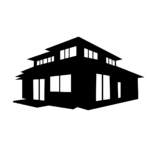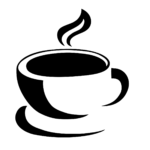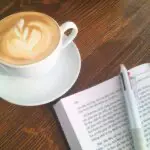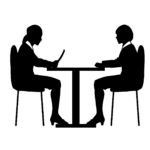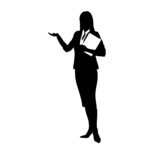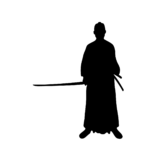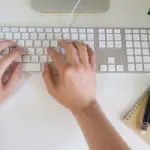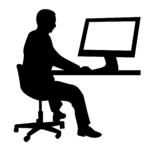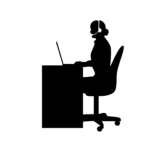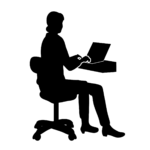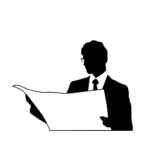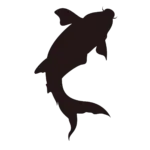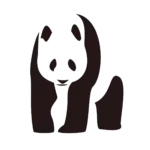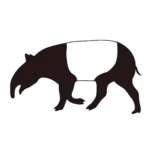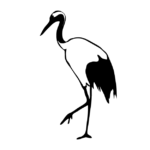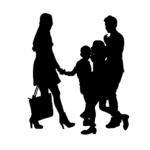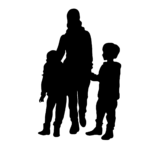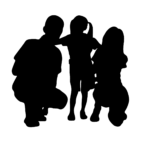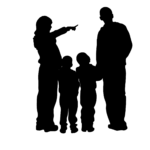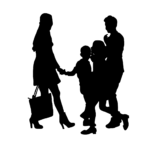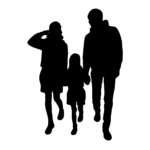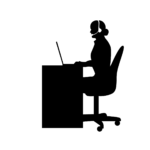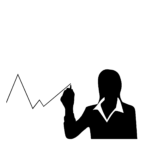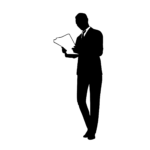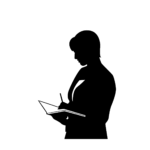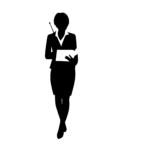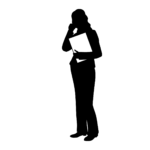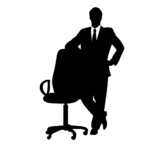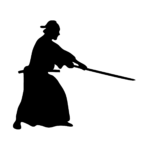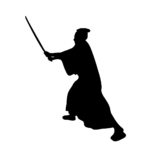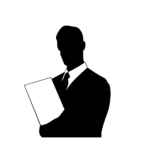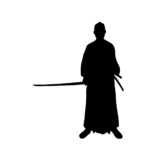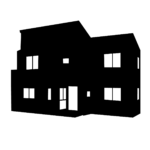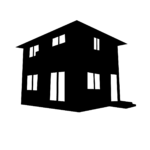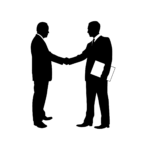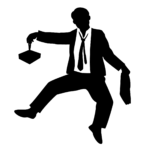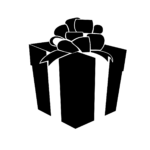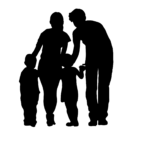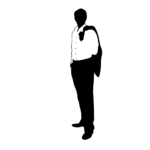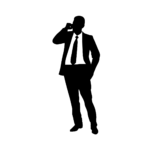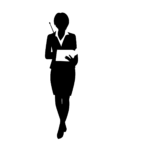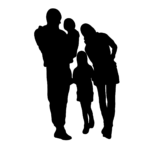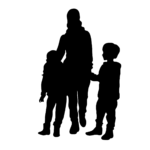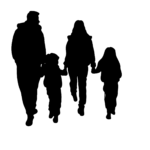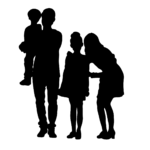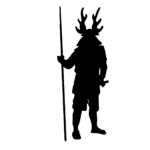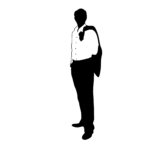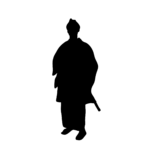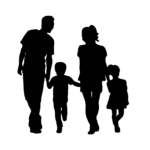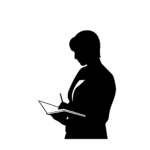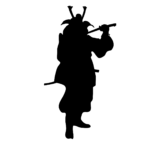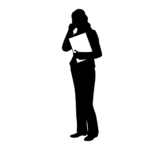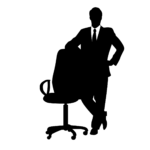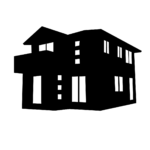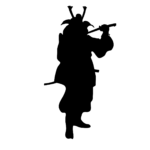離婚協議・財産分与・養育費
離婚や財産分与、養育費に関する話合いは、複雑かつ繊細な問題です。 ちょっとした言葉のニュアンスや話合いの方向性を誤ると、まとまる話もまとまらず、“泥沼”になる 可能性をはらんでいます。
まずは、離婚や財産分与、養育費のご相談を数多く手がける弊所までお気軽にご相談下さい。 弊所の≪対面法律相談≫をご利用頂き、今後の話合いの方向性やその手順について、正しい認識を持つことから始めましょう!
対象となる方
・これから離婚をお考えの方(熟年離婚、浮気・不倫、家庭内暴力等不問)
・離婚準備中でお困りの方 ・離婚したいけれど相手が同意してくれない方
・相手から離婚を要求されてお困りの方 ・双方で離婚することの合意はなされているが、財産分与・養育費・年金分割等の諸条件をこれから協議して決めたい方
・離婚届は出したけれど、財産分与や慰謝料、養育費、年金分割の問題が未解決の方
・夫婦関係調整調停(離婚調停)を申立準備中の方、あるいは調停が進行中の方
お時間ある方は、こちらもお読みください・・・
2007年4月から年金分割も始まり、熟年離婚も含め、離婚者の数は今後ますます増加していくことが予想されます。
離婚自体は、婚姻届を出したのと同じように離婚届を市区町村役場に提出してしまえば簡単にできてしまいますが、離婚問題はそんなに簡単ではありません。
離婚相談は、離婚をした方や離婚をしたい方だけでなく、離婚をしたくない方も是非ご相談ください。
離婚相談の先に、明るい未来があるに違いありません。 離婚に際しては、離婚届を出す前に取り決めをしておかなければならないことがたくさんあります。
夫婦で築いた財産を清算する意味での“清算的財産分与”、離婚後の妻側の自立した生活を援助するための“扶養的財産分与”、離婚原因を片方が作ったということであれば“慰謝料”、未成年の子供がいる場合には“養育費”や“面接交渉権”。

また、既に離婚届を出された方で、もしまだ曖昧になっている事項がある方がいれば、今から一刻も早く取り決めをするべきです。
そして、必ず合意内容は、公正証書による文書化をすることが必要です。
あとで合意内容が反故されることがないように、また後々争い事がおきないように、我々が円満な合意形成を、万全の合意文書作成をお手伝い致します。
特に女性側にとっては、離婚後の生活が成り立つのかどうか不安いっぱいで、なかなか離婚に踏み切れない方も多いです。
弊所では、提携の女性FP(ファイナンシャルプランナー)が離婚後の生活設計をシュミレーション・アドバイスいたしますので、経済的な不安を最大限なくすサポートも致しております。
母子家庭に対する各種助成金などを考慮に入れれば、心配していたほど離婚後の生活は苦しくないケースが実は多いようです。
是非一度、お気軽にご相談下さいませ。 離婚は、夫婦生活にピリオドを打つと同時に、それぞれの新たな再出発でもあります。
しこりや不安を残すことなく、可能な限りの円満な離婚を実現すべく我々がサポート致します。
さあ、勇気をもって、明るく希望に満ちた新生活を始めませんか?
当事者同士ではうまく話ができない方に有効!(当事者間の利害調整役として)
離婚協議をする場合、最も大切なことは当事者間での無用な対立を避けることです。
そのためには、“初動”が肝心です。
話の切り出し方や進め方を間違うと、長期的な紛争に発展する可能性があります。
しかし、きちんとした話し合いのきっかけや話し合いの場さえあれば、話がまとまるケースは実は多いです。
当事者双方が争いを望んでない以上、“話せばわかる”という場合は意外と多いのです。 にもかかわらず、“離婚相談は弁護士だろう”と思い込み、すぐに弁護士に相談される方も多いです。
そうすると、大抵の場合、弁護士から相手方に手紙が行きます。
果たしてこれが、得策でしょうか?
初動としてとるべきベストな手段なのでしょうか?
あなたが弁護士から手紙を受け取った場合を想像してみてください。ほとんどの方は、慌てて弁護士等の法律家に相談に行くでしょう。
「相手方に弁護士がついた以上、素人の自分では手に負えない。費用はかさむが、こちらも弁護人をたてよう。」こうなると思います。
弁護士を立てるというのは、通常、“宣戦布告”に近い強烈な印象を相手方に与えてしまい、態度を硬化させる可能性がかなり高まります。
また、弁護士には相談しないが、いきなり最初から自分で調停を申し立てる方もいます。調停における和解の“落とし所”は、法律上の明確な和解基準がない以上、当事者間の現実的な事情によりある程度決まってきます。特に、養育費については、家庭裁判所作成の「養育費算定表」を基準に話が進められることになります。
従いまして、別に調停を申し立てなくても、調停になったら提案されるだろう和解案は、事前に想定できてしまうケースは多いです。
結論として、いきなり代理人弁護士を立てたり、調停を申し立てたりすることが必ずしも得策とは言えないのです。
当事務所では、ご相談・ご依頼をいただいた場合、まずはご本人からのご連絡(お手紙)をお勧めしています。
もちろん、手紙の文面は当方で全面的に推敲します。 「自分からの手紙を出すのはちょっと・・・」という方や本人からの手紙にリアクションが薄い場合等には、当事務所からご挨拶のお手紙を出します。
ただし、我々は依頼者本人の代理人として手紙を出すのではなく、あくまで穏便な解決を図る中立的な第三者の立場からアプローチをします。
本来の意図は、感情を剥き出しにして相手を打ち負かすことではなく、話し合いの場を設け、喧嘩することなく話を穏便にまとめることです。
そのために我々は全力を注いでそのお手伝いをいたします。
当事務所からご提案する解決案は、仮に調停に持ち込まれても、調停において提案されるであろう客観的合理性をもったものになりますので、調停になっても和解条件が劇的に変わらない以上、任意の交渉過程で納得される方が時間も手間もストレスも少なく済む、というのが相手にとってもメリットとなることでしょう。
確かに双方に代理人弁護士が立つことで話がスムーズにまとまることもあるでしょう。
しかし最初から、高額な費用を払って弁護士を立てまで、話を進めなければならないのでしょうか?
まずは、“争う意はないこと” “できるだけ早く双方納得のできる解決策を探りたいこと”を相手方に伝えることから始めませんか?
そこはもはや法律論の問題ではありません。
感情的な要素が大きく深く影響している問題だからこそ、法律をかざすことが必ずしも解決への近道とは限りません。
あくまで、遺恨を残さない解決を目指します。 弁護士に依頼することは、いつでもできます。
裁判所に調停を申し立てることも、いつでも可能です。
でも、その前に試みてみませんか?
双方が穏便に話し合いのテーブルにつくきっかけを、方法を。 我々はそんなお手伝いをしています。
まずはお気軽にご相談に来てみてください。
ご希望の方には、離婚相談案件に精通した専門の女性スタッフが対応させて頂きますので、女性の方でも安心してご相談下さいませ。
※交渉が決裂した場合は、裁判所へ調停申立てという選択肢もありますし、弁護士をご紹介して事件を引き継ぐことも可能です。
本人だけで離婚調停を進めることのリスク(当事者片方の参謀役として)
離婚及び離婚に伴う諸条件(慰謝料・財産分与・親権者・養育費等)について、夫婦間で話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)を申し立てることができます。
また逆に、夫婦関係がギクシャクしたものを第三者介在の下できちんと話し合いたい場合、別居を解消して夫婦関係を円満に戻したい場合などにも夫婦関係調整調停を申し立てることが可能です。
当事者間の話し合いでは埒(らち)があかない場合に、この調停を利用することは、解決へ向けた一つの大きな糸口になるでしょう。
しかも、代理人弁護士を立てることなく、ご本人が簡単に申立てをすることができるのも利点です。
ただし、この調停といえども万能ではありません。
よく夫婦関係調整調停の結果、調停離婚した方からのご相談を承りますが、裁判所での調停委員の態度・話の進め方に不満を持つ方が多いです。非常に親身に話を聞いてくれる優秀な調停委員も多いでしょうが、調停委員も人間ですので、アタリ・ハズレがあります。
中には、早期の調停成立しか頭にない調停委員もいるようで、提案された調停案に難色を示すと怒られ仕方なく同意させられたということも聞きます。
その結果、どう客観的に見てもおかしな和解条項をみかけることがあります。
夫の収入から見れば、専業主婦の妻にもっと高額な養育費を支払うべきなのに渋々和解させられたケース、履行の取り決めが法的な義務ではなく努力義務的な曖昧な記載になっているケース 等々・・・。
つまり、ご本人で調停を進める場合でも、できれば一度、法律の専門家に意見・アドバイスをもらうことをお勧めいたします。
調停委員の言うことが、必ずしも正しいわけではないですし、調停での主張の仕方によっても和解条件が大きく変わる可能性があるからです。
最近では、ネット上の掲示板を利用した離婚等に関して相互に意見交換・アドバイスするWEBサイトを見かけますが、これはあまりお勧めできません。法律専門家からみると、首をかしげたくなるようないい加減な回答も多く見かけますので、身元も分からないWEB上での匿名の回答を信用するのは大変危険です。
まずは、市区町村役場や弁護士会・司法書士会主催の無料法律相談会でもいいので、複数の専門家にご相談されることをお勧めします。
当事務所では、調停委員も納得し味方につけられるような客観的合理性のある主張のお手伝いをします。
既に調停が進行中の方には、提示された和解案が適正かどうかを精査した上で、より良い条件での和解を目指したアドバイスを致します。 司法書士は、弁護士と違い家庭裁判所における代理権がありません。
したがいまして、調停にはあくまでご本人が、出廷して頂くことになります。
しかし、調停と同時進行で任意の交渉を進めたり、調停期日へ向けた主張や和解案の作成を全面的にサポートいたしますので、弁護士でないことのデメリットは、それ以外はないと自負しております。
司法書士は一般的に弁護士と比べて報酬が低額に設定されておりますので、ご本人での裁判所への出廷が可能であれば司法書士にご相談されるのも一つの選択肢だと思います(ただし、この種の業務をやっていない司法書士の方が多いのが実情ですが)。
まずは、お気軽に当事務所の無料相談もご利用くださいませ。
離婚協議書作成への流れ
解決へ向けた手段の実行について、当事務所にご相談を継続されるかどうかをご検討下さい。 その際には、着手金の有無や金額を含めた御見積もご案内いたします。
当事務所としてさしあたりお手伝いすることがない場合には、相談料のみをいただいて終了になります
着手金のお振込が確認でき次第、相手方との協議内容の確定作業(財産分与・慰謝料・養育費・引越代の負担や親権・面接交渉権に関する合意形成作業)に取り掛かります。
電話・FAX・メール等のやり取りを繰り返し、じっくり内容を固めます。
当事者双方で協議内容に合意が得られれば、最終的にそれを公正証書にする作業に取り掛かります。公証役場における準備手続きは、基本的にすべて当事務所で行いますので、ご安心下さい。
ご希望であれば、財産分与や養育費の支払手続又は受領手続の代行や定期給付がきちんとなされているかを管理する業務もお手伝い致します。
離婚相談の際にご用意いただきたい資料と心構え
当事務所が正確かつ効率的にお話をお伺いし、的確な方向性の示唆・アドバイスができるように、ご相談いただく際にご用意いただきたい関係資料と心構えについて下記にご案内いたします。
なお、ご相談に際して、下記のすべてをご用意頂く必要はありませんが、もし可能であれば、これらをお持ちいただけますとよりスムーズなご相談が可能になるだろうと思います。
特に、財産分与の金額に関してのご相談の場合には、できる範囲内で下記ウ)やエ)の資料があると、より具体的なご相談が可能になるでしょう。
(1)ご用意頂きたい資料
ア)戸籍謄本
イ)住民票
ウ)ご夫婦の財産一覧のメモ(預貯金、有価証券、保険・年金、 自動車・不動産の名義人や評価額、住宅ローン等の借入額、ご夫婦の収入)
エ)上記ウに関する資料 ・不動産登記簿謄本 ・預貯金通帳 ・証券会社の運用報告書等 ・保険証券 ・自動車の車検証 ・負債に関する残高証明書(返済計画書)等 ・源泉徴収票(確定申告書)
(2)整理しておくべき事項
・家庭の現状(年齢、職業、年収、家計、健康状態、親族関係等)
・ご本人及び相手方の意思・意向(離婚? 別居?)
・今後の手続の進め方の希望(仲裁役? 一方の代理人?)
・離婚条件(財産分与・慰謝料・養育費・子の親権・面接交渉権)
・離婚後の生活設計(住居・仕事・収入)
(3)ご相談に際しての心構え
・感情的にならずに、冷静に客観的な事実を話す
・自分側に不利な部分も含めすべてを隠さず話す
離婚相談の報酬基準(消費税込)
ご相談料
・弊所代表 宮田対応:13,200円(税込)/80分(30分以内なら6,600円)
・宮田以外対応:11,000円/80分(30分以内なら5,500円)
※2回目以降は、30分につき6,600円(税込)を基本とさせて頂いております。
・協議の内容がほぼ合意できている場合(離婚協議公正証書作成):88,000円より
・離婚協議・財産分与協議のお手伝い:13.2万円より(着手金必要、分割払い可)