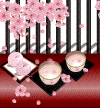『受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならない』(信託法第30条)という大原則の下、受託者は信託目的を実現するために職務を全うします。
そして、受託者は、日々の財産管理において『信託財産に関する帳簿』を作成するとともに、少なくとも毎年1回、1年分の貸借対照表・損益計算書等の作成をする義務があります(信託法第7条第1項・第2項)。
また、受託者は、それらの書類を長期にわたり保存する義務を負っています(信託法第37条第4項~第6項)。
なお、この受託者の書類等の作成・保存義務は強行規定であって、信託契約書の中で義務を免除することは、受益者にとって不利な定めとなるので、たとえ受益者が容認したとしてもできないとされます。
一方、受託者の受益者に対する「報告」は、受益者の受託者に対する監督的機能を実行的にする視点から、原則として報告義務を負わせているものの、信託契約書の中でその義務を軽減・免除することが可能とされています(信託法第37条第3項)。
ただ、冒頭の大原則に従い、かつ信託とは受益者のための財産管理であるという信託の本質からみれば、受益者が受託者の財産管理状況を知りたいと思った時には、知る権利を守る必要があります。
そこで、信託法では、受益者側からの帳簿等の閲覧・謄写請求権について、きちんと保証しています(信託法第38条)。
結論としては、単独受益者からの請求の場合、又は複数受益者全員からの請求の場合(他にその利益を保護すべき受益者が存在しない)は、信託財産に関する帳簿等(残高や資産の増減が分かる資料)や貸借対照表・損益計算書などについて、信託契約書にどのように定めても、あるいはどのような理由があったとしても、受託者は開示する義務がある(受託者は受益者からの開示請求を拒めない)ということになります(信託法第38条第3項)。