-

-
交通事故死の損害賠償金
交通事故により死亡した場合、遺族が加害者から受け取る損害賠償金は相続税の対象とはなりません。 この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、税金はかかりません。 損害賠償 ...
-

-
相続税における配偶者の税額軽減
2008/11/22 相続税
相続税における配偶者の税額軽減制度とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、下記の(1)と(2)の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。 ...
-

-
株券電子化の方法とメリット
「株券電子化」は、平成21年1月5日に実施されます。 株券電子化(株式のペーパーレス化)とは、「社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債株式等振替法」という。)」により、上場会社の株式等に係る株券を ...
-

-
相続税の申告と納税
2008/11/22 相続税
相続税の申告と納税は、相続や遺贈によって取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含みます。)及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計額が基礎 ...
-

-
清算型遺贈における不動産登記手続き
「清算型遺贈」とは、自分が亡くなったら、不動産など遺産の全部又は一部を売却処分して現金化し、その換価代金を遺言に基づき自分の希望する相手に遺贈する手続きのことを言います。 清算型遺贈における不動産登記 ...
-

-
法定後見人の権限のまとめ ―早分かり法定後見制度3類型―
成年後見制度は、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律的部分や財産管理を中心とした生活面で本人を支援する身近な仕組みです 判断能力が既に ...
-

-
保佐監督人、補助監督人 【法定後見】
保佐人、補助人も代理権を持つことがあり、また本人の生活、健康に関する職務も行うことから、その権限が濫用されることが本人に大きな損害や危険をもたらすおそれがあります。 そこで、保佐、補助にも監督人制度が ...
-

-
補助人の職務・成年後見の補助が終了するとき 【法定後見】
補助人の主な職務は、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に対し適切に同意を与える、本人の行為を取り消す又は代理権の行使をすることです。 そして、それらの内容について ...
-

-
補助開始の効果 ―補助人の権限― 【法定後見】
同意権・取消権 補助の対象者は、比較的高い判断能力を有しているので、家庭裁判所が「特定の法律行為」について補助人の同意を得なければならないことを定めることができます(「同意権の付与の審判」)。 これは ...
-

-
補助開始の審判申立て 【法定後見】
「補助」は、「事理を弁識する能力が不十分な人」について、家庭裁判所が「補助開始の審判」をすることによって開始します。 「事理を弁識する能力が不十分」とは、不動産や自動車の売買などの重要な行為は一人でで ...
-
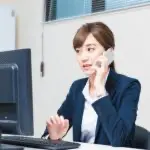
-
保佐開始の効果 ―保佐人の権限― 【法定後見】
≪同意権・取消権≫ 本人が、不動産や自動車の売買などの重要な行為を行うには、保佐人の同意が必要となります(これを、保佐人の側からとらえて、「同意権」と言います)。 本人が、保佐人の同意を得ずに行った場 ...
-

-
成年後見の「保佐」とは?「保佐人」の職務と「保佐」が終了するとき
「保佐」とは? 「保佐」は、精神上の障害の為、判断能力が著しく低下している人のための制度です。 「保佐」では、本人(被保佐人)の残された能力を生かすために、本人が自ら契約をすることを前提としています。 ...
-

-
保佐開始の審判申立て 【法定後見】
「保佐」は、「事理を弁識する能力が著しく不十分な人」について、家庭裁判所が「保佐開始の審判」をすることによって開始します。 「事理を弁識する能力が著しく不十分」とは、日常の買い物程度は一人でできるが、 ...
-

-
成年後見の「保佐人」の職務 【法定後見】後見人と被後見人との利益相反 【法定後見】
後見人は、被後見人の財産管理に関する包括的な代理権を有しています。 しかしながら、後見人と被後見人との利益が相反する場合には、公正な代理権の行使を期待できません。 この場合、後見人は被後見人を代理する ...
-

-
後見人による預貯金の財産管理で注意すべきこと【法定後見】
後見人の職務である財産管理とは、被後見人の財産を適正に管理することです。 具体的には、 印鑑や貯金通帳の保管・管理 不動産の維持・管理 保険金や年金などの受領 介護サービス等の締結 必要な経費の支出 ...
-

-
不動産の管理と居住用財産の処分許可 【法定後見】
被後見人の居住用不動産を処分(売却、賃貸、抵当権の設定など)する必要がある場合には、必ず事前に家庭裁判所に「居住用不動産の処分許可」という申立てをして、その許可を得る必要があります。 その他の不動産に ...
-

-
支出の管理 【法定後見】
被後見人の財産から費用を支出する際には、それが被後見人のための適正な出費であることが当然必要ですが、「限りある財産を有効に利用する」という視点が必要です。 その管理にあたっては、以下に注意しなければな ...
-

-
収入の管理 【法定後見】
2008/8/5 法定後見
被後見人の収入としては、給与や年金・不動産収入・生活保護費などが考えられますが、必ず、被後見人名義の口座(または「後見人が管理している被後見人の預貯金」であることが明確に表示してある口座)にて管理する ...
-

-
成年後見人の職務「身上監護」について 【法定後見】
後見人の職務である「身上監護」とは、被後見人の生活、治療、療養、介護などに関する法律行為を行うことをいいます。 被後見人の住居の確保及び生活環境の整備、施設等への入退所の手続きや契約、被後見人の治療や ...
-

-
成年後見監督人の職務・選任・報酬 【法定後見】
成年後見人は、本人の財産管理から生活や療養看護、介護の手配まで幅広い権限を持ちますので、その権限を濫用したり、逆に任務を怠ると、本人の生活、健康、生命まで脅かされる可能性もあります。 成年後見に対する ...




