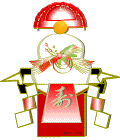家族信託の受託者の「辞任」と「解任」についてまとめてみました。
家族信託の受託者の「辞任」と「解任」についてまとめてみました。
【 目 次 】
1.受託者の辞任について
2.受託者の解任について
3.新受託者の選任について
1.受託者の辞任について
受託者が辞任をするには、信託行為に別段の定めがある場合を除き、原則、委託者及び受益者の同意を得て辞任することができます(信託法第57条第1項)。
なお、実務上は、「委託者兼受益者」という形態がほとんどですので、実質的に受益者単独の同意で辞任が可能ということになります。
受託者が辞任をしたい時点で、受益者側が認知症等で同意する能力を喪失している場合は、辞任ができないことになってしまいますので、その場合は、「やむを得ない事由がある場合」という信託法第57条第2項の規定に従い、「裁判所の許可」を得て辞任することになります。
なお、裁判所に対し、辞任の許可を申し立てる場合は、その原因となる事実(やむを得ない事由を証する事実)を疎明しなければなりません。
受託者の義務と責任は重大ですので、受益者が不利益を被ってしまうこと等を回避するためにも、辞任をする際には裁判所の許可が必要とされています。
実務においては、裁判所に申し立てをするケースはほとんどないでしょうし、そのような煩わしい裁判所の手続きを排除するためにも、辞任せざるを得ない状況になっても困らないように備えたいというニーズがあれば、信託契約書の設計の段階で、辞任しやすいような条項を設けておくことも一考です(信託法第57条第1項但書による「別段の定め」)。
2.受託者の解任について
委託者及び受益者は、いつでも、その合意により受託者を解任することができます(信託法第58条第1項)。
前述のとおり、実務上は、「委託者兼受益者」という形態がほとんどですので、実質的に受益者単独の判断で受託者の解任が可能ということになります。
解任について検討すべきポイントは、3つあります。
一つ目は、委託者兼受益者の気分次第で(委託者兼受益者は高齢のため正しい事実を認識できなくなる可能性もありますので)いつでも気軽に解任できないように、一定の要件を満たす場合にのみ解任できるような「解任事由」を設けておくことはお勧めです。
二つ目。もし受託者が突発的な交通事故や急病で判断能力が無くなってしまうと、自主的に辞任する余地がないので、受託者を交代させることも難しくなります。
従いまして、不測の事態に対応できるように、受託者を解任できるような定めを置くことは良策です。
三つ目は、受託者が万が一不義理を働いた場合に備える必要性です。
受託者が受益者のためではなく、魔が差すなどして受託者の私利私欲に走ってしまった場合、その受託者を解任したくても、その時点で受益者にそれを判断する能力が無くなっている場合には、周囲の家族も手が出せないような事態に陥りかねません。
そのような事態に備え、受益者に代わって、受益者代理人や信託監督人が解任できるような条項を設けておくことも一考です(信託法第58条第3項)。
3.新受託者の選任について
信託が終了等する前に受託者が「辞任」又は「解任」により不在となる場合、信託契約書において予め指定された後継受託者(第二受託者や第三受託者)がいれば、その者が新たな受託者となります。
後継受託者に関する定めがないとき、又は信託契約書に後継受託者となるべき者として指定された者が就任承諾をせず、若しくはこれをすることができないときは、委託者及び受益者は、その合意により後継受託者を選任することになります(信託法第62条第1項)。
受託者が後継受託者を選任すべきときに、受益者にそれを判断する能力が無くなっている場合に備え、実務上は、信託契約書の設計の段階で、第二受託者・第三受託者等の後継受託者の指名しておく条項を設けることも多いです。