-

-
成年後見人が参加する遺産分割協議の注意点 【法定後見】
被後見人が相続人となっている遺産分割の協議にあたっては、当然ながら後見人が被後見人を代理することになります。 その協議にあたっては、原則として、被後見人が最低でも法定相続分を取得する必要があります。 ...
-

-
家庭裁判所による監督 【法定後見】
【成年後見人等に対する監督権限】 家庭裁判所は、成年後見人等に対し、一般的な指導、監督権限を持ちます。 具体的には、?いつでも成年後見人等に対して、後見等の事務の報告、財産目録の提出を求め、?後見等の ...
-

-
被後見人が無資力の場合 【法定後見】
被後見人に財産や収入がない場合、被後見人の生活費(入院費などの一切を含む)は、被後見人の扶養義務者が単独又は共同で負担しなければなりません。 後見人だからといって、それらの費用を負担する義務はありませ ...
-

-
成年後見人等の報酬 【法定後見】
成年後見人等の報酬は、家庭裁判所が適正額を決め、本人の財産から支払われます。 成年後見人等がその職務を行うのに必要な費用も本人の負担となります。 保佐人、補助人の場合も同様です。 報酬の付与 成年後見 ...
-

-
成年後見登記制度 【法定後見】
従来は、禁治産・準禁治産宣告がなされた事実が公告され,併せて戸籍に記載されていましたが、新しい成年後見制度では公告の制度は廃止され、戸籍への記載に代わる新たな公示制度として成年後見登記制度が創設されま ...
-

-
成年後見人等の辞任・解任 【法定後見】
【辞任】 後見人は、被後見人の権利や財産を守るために、家庭裁判所から適任者と認められて選任されたわけですから、自らの都合で自由に辞任することはできません。 辞任するには、家庭裁判所に対し申立てをし、辞 ...
-

-
成年後見が終了するとき 【法定後見】
2008/8/5 法定後見
成年後見は、後見開始の審判の取消し、および本人の死亡により終了します。 後見開始の審判の取消し その原因がなくなったとき、すなわち「保佐」程度以上に判断能力が回復した場合になされます。 但し、当然に終 ...
-

-
成年後見人等の選任基準と資格 【法定後見】
成年後見人等は、家庭裁判所等が、一切の事情を考慮して適任者を選びます。 「後見開始の審判」「保佐開始の審判」「補助開始の審判」をする場合には、家庭裁判所は、必ず成年後見人、保佐人、補助人(以下、この三 ...
-

-
成年後見人の職務 ―後見業務の注意点― 【法定後見】
成年後見人に選任された人は、まず財産目録を作成し、家庭裁判所に提出するとともに、年間の収支予定を立てなければなりません。 成年後見人の主な職務は、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に ...
-

-
成年後見開始の効果 ―後見人の権限― 【法定後見】
「保佐」や「補助」と異なり、成年後見人が事前に同意を与えていても、取り消すことができます。 ただし、食料品や日用衣料品の購入など、日常生活に関する行為については取り消すことができません。 例えば不動産 ...
-

-
法定後見制度とは? ―法定後見人3類型の比較― 【法定後見】
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。 「任意後見」は、元気なうちに任意後見契約を交わす、いわば“転ばぬ先の杖”の制度です。もう一方の「法定後見」は、判断能力が既 ...
-

-
任意後見契約と法定後見の関係(優先順位)
任意後見と法定後見では、任意後見を優先させるのが原則です。 任意後見は、本人の意思に基づく後見制度であり、自己決定権の尊重の理念から、任意後見を優先させることになります。 しかし、「本人 ...
-

-
見守り契約とは
任意後見契約は交わしたが、いつから任意後見をスタートさせるかというのは、非常に大事な問題です。 その対策として、一般的に任意後見契約の締結とセットで交わされるのが「見守り契約」というものです。 この契 ...
-

-
任意後見の終了 【任意後見】
任意後見契約は、以下の事由の発生によって終了しま す。 1. 任意後見人の解任 任意後見人に不正行為、著しい非行跡、その他任意後見人としてふさわしくない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見人を解任 ...
-

-
任意後見契約の変更・解除 【任意後見】
任意後見契約のうち、代理権にかかわるもの、すなわち下記(1)から(3)は、契約の変更によってすることはできません。 (1) 代理権の範囲の変更 (2) 第三者の同意・承認を必要とする特約の追加・廃止 ...
-

-
任意後見人の死亡と任意後見の継続 【任意後見】
任意後見人の死亡により任意後見契約は終了します。 任意後見人が死亡すると、任意後見監督人は、死亡による任意後見終了の登記をしたうえで、任意後見人の遺族に、受任事務の終了の報告、管理の計算をするように求 ...
-

-
任意後見契約公正証書の必要書類と費用 【任意後見】
任意後見契約は、公正証書にしなければ効力が発生しません。 公正証書にするためには、公証人役場で公正証書にする手続をしなければなりません。 公正証書にする手続に必要な書類は、原則として以下のとおりになり ...
-

-
任意後見人の報酬 【任意後見】
任意後見契約は、委任契約の一種です。 したがいまし、任意後見人は、被後見人本人が元気だった時に交わした「任意後見契約」の中で取り決めをしておかなければ、任意後見人としての報酬を受け取ることができません ...
-
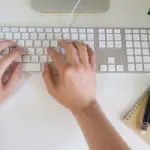
-
任意後見人に対する監督 ―任意後見監督人の職務― 【任意後見】
法定後見では、原則として家庭裁判所自らが直接成年後見人等へ監督を行いますが、任意後見では、任意後見監督人が必ず置かれ、その任意後見監督人が任意後見人に対し監督をします。 家庭裁判所が直接任意後見人を監 ...
-

-
相続税がかからない遺産(非課税財産)
国民感情や社会政策的見地から、相続税がかからない財産(非課税財産)が定められています。 非課税財産の主な例は、下記のとおりです。 ◎ お墓や仏壇、仏具 ◎ 一定の公益事業を行う人で、取得財産をその公益 ...




