-

-
相続・遺産整理手続きにおける相続人調査
家族が亡くなった場合、亡くなった方(被相続人)名義の財産に関し、銀行や証券会社での相続手続き、保険会社への保険金請求、法務局への相続登記申請など様々な手続きが必要となります。 その手続きの際には、被相 ...
-

-
家族信託における「委託者の地位の承継」と登録免許税
世の中に出回っている家族信託・民事信託の契約書の文例において、「委託者の地位は、相続により消滅し相続人に承継されない」という条項を非常に多く見かけます。 このような条項を置くことの趣旨は、委託者兼当初 ...
-

-
改めて知っておきたい! 遺言書作成時の注意点2つ
遺言書を作成する際には、気を付けなければならない点がいくつもあります。 今回は、その代表格として、「予備的条項(予備的遺言や補充遺言とも言われます)」と「遺言執行者」についてご説明します。   ...
-

-
配偶者居住権とは? 制度概要・活用例・家族信託との比較を分かりやすく解説【2020年最新版】
「配偶者居住権」とは、2020年4月1日施行の改正民法により創設された制度で、相続発生により遺された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦で共有する建物でも可)に居住していた場合に、相続発生後も配偶者が ...
-

-
遺留分として不動産を譲渡した場合の課税リスク
「遺留分」とは、相続に際し、法定相続人の生活保障のために民法が最低限保証した遺産を貰える権利のことを言います。 この遺留分については、2019年7月1日施行された民法改正により、大きな変更がなされまし ...
-

-
民法改正とマンション管理費の時効について
これまで、マンションの管理費・修繕積立金(以下、「管理費等」と言います。)は、民法169条に規定する「定期給付債権」にあたり、「5年」の短期消滅時効が適用されていましたが(管理組合が5年の間に裁判を起 ...
-

-
債務引受・債務免除で贈与税が課税されるリスクに注意!「みなし贈与」とされる典型的な3つのケース
一般的には、個人間における無償での財産の譲渡(例:太郎さんが持っているものを“ただ”で花子さんにあげる行為)に対して、贈与税の課税がなされるイメージですが、必ずしもプラスの財産を移動だけが贈与税の課税 ...
-

-
所有権に基づく物件的請求権の消滅時効
売買による所有権移転仮登記に関し本登記請求権の消滅時効成立の可否 「所有権に基づく物件的請求権」とは、不動産を購入した買主が売主に対し不動産の引渡請求や所有権移転登記請求をできる権利をいいます。 建物 ...
-
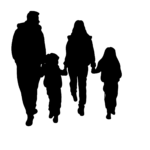
-
民法改正後の相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)の法的効力
2019年の民法改正で変わった遺言の効力 特定の財産を特定の相続人に確実に承継させたい場合、遺言書の中で、例えば「下記の不動産を長男に相続させる」などと記載することはごく一般的です。 このような“特定 ...
-

-
家族信託の税務における「損益通算禁止」注意点のまとめと具体例【最新版】
家族信託の税務における注意点の一つに「損益通算禁止」が挙げられます。 「損益通算禁止」とは? 個人の確定申告においては、毎年1月1日から12月31日までの1年間における所得を全てまとめて申告することが ...
-

-
「遺産整理」は、弁護士・信託銀行に頼んではいけない!
遺産整理は、弁護士・信託銀行に頼んではいけない。 これは、弁護士・信託銀行に対する批判や悪口ではありません。 「真実」です。 弁護士や信託銀行員自身も、特別な事情がない限り、自分の家族・親族・親友の相 ...
-

-
家族信託の契約終了時の実務
家族信託の終了に伴う実務については、新聞・雑誌・テレビ等で取り上げられると共に、士業等の専門職側も家族信託の設計・実行に積極的に関わることが増えてきたのが、ここ数年であるというのが実状ですので、まだま ...
-

-
不動産会社が家族信託のコンサル業務をするメリットとリスク
不動産オーナー・地主・資産家などから収益物件の賃貸管理を預かる不動産管理会社や売買仲介・賃貸仲介を行う不動産会社、あるいは自宅・アパート・賃貸併用住宅の提案をするハウスメーカーのお客様で、所有者・施主 ...
-

-
民法(債権法)改正の重要ポイントまるわかり【2020年4月】
民法(債権法)改正法が2020年4月1日に施行されました。 様々な部分で大きな改正が行われましたが、我々の日常生活や一般的なビジネスにおいて重要となる知っておくべきポイントを3点挙げて、分かりやすく解 ...
-

-
家族信託の受託者の帳簿作成・保管・報告義務のまとめ
家族信託における受託者の帳簿等作成義務、保管義務、受益者への報告義務等について、簡単にまとめてみました。 (※1)信託事務に関する計算、信託財産に属する財産、信託財産責任負担債務について ...
-

-
民法(債権法)改正が不動産賃貸借契約に与えるポイントを分かりやすく解説【2020年4月最新版】
2020年4月1日から民法の債権法に関する分野の改正が施行されました。 これにより従来の不動産賃貸借契約におけるルールが大きく影響を受けることになります。何がどう変わるのか、重要な3つのポイントに分け ...
-

-
家族信託の契約書におけるリスクのある信託終了事由について
弊所では、個人のお客様からのセカンドオピニオンサービスを実施しておりますし、全国の法律専門職や金融機関等からの依頼に基づき、家族信託の契約書のリーガルチェック・作成指導をさせて頂いています。 毎月50 ...
-

-
証券会社で家族信託の信託口口座を作成するための信託契約作成時の注意点
この度、大手証券会社が家族信託に対応できるようになりました。 つまり、家族信託の契約書をもとに証券会社で“信託口口座”、 いわゆる「証券信託口口座」が作れるようになりました。 そして、今後もこの流れは ...
-

-
複数の委託者のうちの一部の者を受託者とする家族信託の可否について ~委託者兼受益者ABC、受託者Aとする信託設計~
3人共有の不動産をその共有者の一人を受託者として管理処分権限を一人に集約させるという家族信託の設計について検討します。 具体的には、長男A・二男B・三男Cが各3分の1ずつ保有する共有不動産を信託財産と ...
-

-
家族信託における税務署への提出・届出書類のまとめ
家族信託に関係する税務署への届出については、下記の4つの場面に分けて考える必要があります。 家族信託に関係する税務署への届出書類の4つの場面 ㋐ 家族信託開始時に税務署に提出する書類 ㋑ 信託契約期間 ...




