-

-
新株予約権
2010/5/1 新株予約権
新株予約権とは、株式会社に対して行使することにより、当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいいます。 予め定められた行使価格を時価が上回っている場合は、権利行使すれば利益が得られ、逆に予め ...
-

-
自己株式取得手続きのまとめ
自己株式の取得の態様は幾つかありますが、ここでは株主との合意に基づく任意的な取得についてご紹介します。 1.株主全員に譲渡しの機会を与えて取得する方法 (1)株主総会の決議(会社法第156条) 会社が ...
-

-
自己株式の取得の意義
2010/5/1 株式
自己株式はかつて「金庫株」と呼ばれ、その取得は原則禁止されていたものでしたが、現在ではその取得数や取得目的の制限はなく、取得は自由になっています。 自己株式を取得する意義としては、以下のようなものが代 ...
-

-
一般社団法人・一般財団法人の登記事項
一般社団法人の登記事項 「※」印は、定めた場合のみ登記事項になります。 目的 名称 …名称中には一般社団法人なる文字を使用しなければなりません。 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所 存続期間又は解 ...
-

-
一般社団・財団法人の税制優遇措置 ≪非営利型法人≫
一般社団法人・一般財団法人は、原則として法人税法上、普通法人として全所得が課税対象となります(株式会社等の営利法人と同じ扱いです)。 ところが、一般社団法人・一般財団法人でも税制優遇措置が受けられる場 ...
-

-
一般財団法人設立のメリットとデメリット
様々な任意団体が一般財団法人制度を利用することができるようになったので、一般財団法人を設立することのメリットとデメリットを確認してみましょう。 ≪メリット≫ ・法的要件を満たせば登記によって設立できる ...
-

-
一般社団法人設立のメリットとデメリット
2010/4/30
様々な任意団体が一般社団法人制度を利用することができるようになったので、一般社団法人を設立することのメリットとデメリットを確認してみましょう。 ≪メリット≫ ・法的要件を満たせば登記によって設立できる ...
-

-
役員の責任限定
取締役や監査役は、会社に対して善良な管理者の注意義務を負担しており、法令や定款に違反して会社に損害を与えた場合は、損害賠償義務が発生します。 そして、株主は株主代表訴訟制度により会社を代表して役員に対 ...
-

-
権利能力なき社団と登記
権利能力なき社団とは、社団(=人の集まり)としての実質は備えていても法人格を有していない団体を言います。 社団としての実質とは、判例によると ・一定の規則をもつこと ・団体内部の管理が多数決で処理され ...
-

-
不在籍証明書・不在住証明書とは
一般的に、“不在籍不在住証明書”とまとめて言われることの多いこの証明書は、申請した本籍(または住所)及び氏名に該当する戸籍や住民登録がないことを証明する市区町村発行のものを言います。 どういう場合にこ ...
-

-
登記識別情報通知とは
2010/4/22 不動産登記
登記識別情報とは、平成17年3月7日より施行された新不動産登記法により、従来の権利書に代わるものとして導入されたもので、登記の名義人となる申請人(登記権利者)に法務局(登記所)から権利書に代えて発行さ ...
-

-
「遺言信託」という言葉について
本来の法律用語として「遺言信託」の意味は、「遺言で設定する信託」のことです。 しかし、信託銀行が取り扱う業務(商品名)として「遺言信託業務」という名称を使い始め、それが一般的に普及されてしまいました。 ...
-

-
遺言書と遺書の違い
「遺言書」とは 「遺言書」は、法定の厳格な要件を備えた法律的に効力をもつ文書(英語で「will」)です。 法律的に効力を持つとは、つまり、法律上の財産権や身分権に直接影響を及ぼす文書と言うことができる ...
-

-
遺言書の検認
遺言書が公正証書遺言以外の形式で作成されている場合は、相続発生後、家庭裁判所の検認を経なければ、それを使用して遺言執行・遺産整理手続に入ることができません。 『検認』とは、相続人に遺言の存在・内容を知 ...
-

-
遺言ができる人・遺言書を作れる人
満15歳に満たない者は、遺言をすることができません。 しかし、一般的な法律行為を未成年が行うときには親(法定代理人)の同意や代理が必要なのに対し、遺言は満15歳以上であれば未成年であっても親権者の同意 ...
-

-
非居住者への“管理協力金”の徴収は「適法」との最高裁判決
2010/2/11 マンション管理費
2010年1月26日、非居住者への“管理協力金”の徴収は「適法」との最高裁判決が出ました。 ◆最高裁判決の概要◆ 判決の要旨は、以下の通りです(出典 毎日新聞〈毎日jp〉より)。 マンションの管理組合 ...
-

-
遺言執行者の任務(職務権限)
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法第1012条1項)。 また、遺言執行者がいる場合には、相続人は、遺言の対象となった相続財産の処分その他遺言の ...
-

-
相続放棄と代襲相続
相続放棄した場合、その相続人は初めから相続人ではなかったことになりますので、代襲相続は起こらないことになります。 ■相続放棄と代襲相続 例えば、「父親が亡くなり配偶者と子供が法定相続人」となった場合、 ...
-
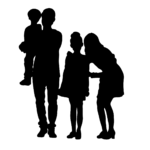
-
遺言公正証書の存否の検索方法
平成元年1月以降に作成された遺言公正証書については、全国の公証役場において「遺言検索システム」による検索・照会を行うことができます。 ◆申請人 相続人その他の利害関係人(受遺者、遺言執行者等)及びそれ ...
-

-
寄与分とは~特別の貢献者、通常の相続分に加えその貢献分を上乗せする~
特定の相続人が、他の相続人に比べて、特に被相続人に貢献している場合があります。 長い間、療養看護に努めたり、事業に協力して、財産の維持や増加に貢献した場合などです。 このような場合に、他の相続人と同じ ...




