-

-
被後見人名義の不動産の換価処分と後見監督人・家裁の同意
被後見人名義の不動産の処分については、後見監督人の同意や家庭裁判所の許可が必要な場合とそうでない場合があります。 以下に場合分けして、整理いたします。 (1)任意後見人が就任している(任意後見監督人が ...
-

-
親族が後見人に就任する際の注意事項(禁止事項)
親族が後見人に就任する際の注意事項は、下記のとおりです。 下記の禁止事項・注意事項に抵触した場合、家庭裁判所から解任される可能性もありますのでご注意ください。 1.無断借用・使い込み・流用の禁止 ⇒業 ...
-

-
初心者向け“成年後見に関する法律用語”の解説
◆カ行◆ 鑑定:本人に判断能力がどの程度あるかを医学的に判定するための手続き。 鑑定人:本人の判断能力について鑑定を行う者。精神科医である必要はなく、通常はかかりつけの医師がなることが理想的。 居住用 ...
-
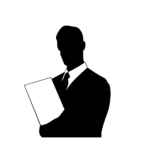
-
海外居住のため印鑑証明書を添付できない場合の登記手続き
日本に住民票登録をしていないと、印鑑証明書を発行してもらうことはできませんので、海外赴任等で海外に居住されている方は、実印や印鑑証明書というものを利用することができません。 したがって、不動産を売却す ...
-
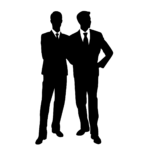
-
死後事務委任契約とは
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が受任者に対して、自己の死後の葬儀や埋葬等に関する事務についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する委任契約をいいます。 あくまで“事務手続き”になりま ...
-
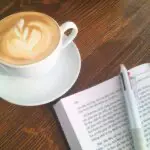
-
既存の任意団体を一般社団法人化する場合の注意点
既存の任意団体、特に規模の大きな任意団体(例えば特定の医師が集う学会、各種業界団体等)が一般社団法人化する場合には、以下の点に注意する必要があります。 1)法人の存在意義の見直し まずは根本的な問題と ...
-

-
過払い金返還請求権の時効消滅
過払い金返還請求権も民事上の請求権として、原則10年の時効期間が経過した後には実質的に請求が出来なくなります(時効により請求権が消滅します)。 過払い金の返還請求において、相手業者から消滅時効が主張さ ...
-

-
電子公告制度 その1
電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律(平成16年法律第87号)の施行により、平成17年2月1日から、株式会社の公告方法につき、「官報」「日刊新聞紙」に加え、インターネットのホームページ ...
-

-
電子公告制度 その2
◆電子公告手続きの流れ 電子公告制度を導入した場合の手続の流れは、下記のようになります。 (A)定款に電子公告を公告方法とする旨を定める(既存の会社は定款変更決議) ↓ ↓ ↓ (B) ...
-

-
審判離婚とは
調停離婚というのは基本的に当事者双方の合意がなければ成立しないものですが、一方が離婚を承知しなくても、家庭裁判所が独自の判断の下に職権で離婚を宣言する方法があります。 「審判離婚」と呼ばれるものです。 ...
-

-
過払い金の返還請求で最高裁判所が時効認めず!【最高裁が初判断】
過払い金の返還をめぐって、借り手側がいつまでさかのぼって返還請求できるかが争われた裁判で、最高裁第1小法廷は1月22日、『一連の貸借取引が終了時より10年以内は請求できる』とする借り手側に有利な判断を ...
-

-
今さら人には聞けない「株券電子化」の要点整理!
「株券電子化」は、平成21年1月5日に実施されました。 昨年は、この株券電子化の話題が政府や証券会社から盛んに情報発信していましたが、まだよくご存じない方もいるかもしれません。 そこで、今さらなので人 ...
-
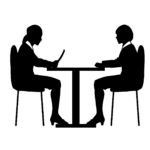
-
養育費の増額請求について
養育費の取り決めをした時点から当事者の一方または双方に様々な事情変更があった場合には、その額を変更する必要が出てくることがあります。 当事者の話し合いで合意がなされれば、増額も減額も問題ありませんが、 ...
-
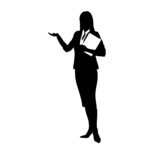
-
離婚調停の不成立
調停の場に当事者が出頭しない場合には調停不成立として事件は終結しますが、いくら話し合っても当事者間で合意が成立する見込みがない場合も調停は不成立として終結します。 調停不成立の処置には不服申し立てはで ...
-

-
調停離婚の手続き
申立人 夫もしくは妻 調停を申し立てるのは夫か妻のどちらかであり、親や兄弟など第三者が申し立てることはできません。 訴訟の場合は離婚の原因をつくった有責配偶者からの訴えの提起はかなり難しいものですが、 ...
-
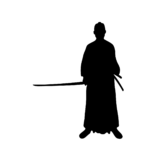
-
調停離婚とは
当事者間の話し合いで決まる協議離婚がスムーズにできればそれに越したことはありませんが、いくら協議しても離婚の合意ができないときや、相手が話し合いすら拒んでいるようなときは協議離婚は不可能です。 このよ ...
-

-
企業法務・商業登記の「オフバランス(オフバランス化)」とは
「オフバランス(オフバランス化)」とは 「オフバランス」あるいは「オフバランス化」というのは、 資産や負債をバランスシート(貸借対照表)上の記載からなくすことを指します。 いわゆる「簿外資産」「簿外負 ...
-

-
相続人に養子がいる場合の税務上の法定相続人の考え方
相続税の計算をする場合、法定相続人の数が関係する項目が下記のとおり4つあります。 (1) 相続税の基礎控除額の計算をするとき。 (2) 生命保険金の非課税限度額の計算をするとき。 (3) 死亡退 ...
-

-
死亡保険金の税務上の取扱い
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。 この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を ...
-

-
相続財産から控除できる葬式費用
2008/11/22 相続
相続税を計算するときは、被相続人の葬儀にかかった費用を遺産額から差し引くことができます。 葬式費用となるもの 遺産額から差し引ける葬式費用として認められるのは、通常次のようなものです。 ...




