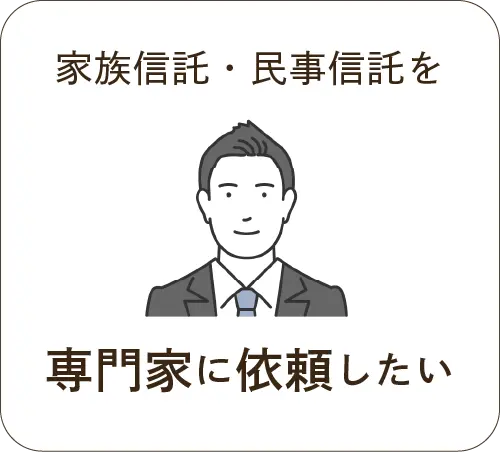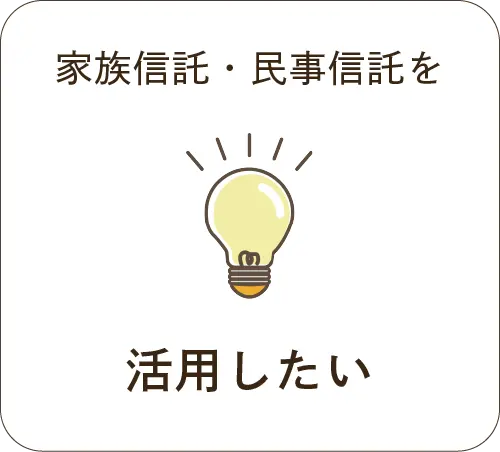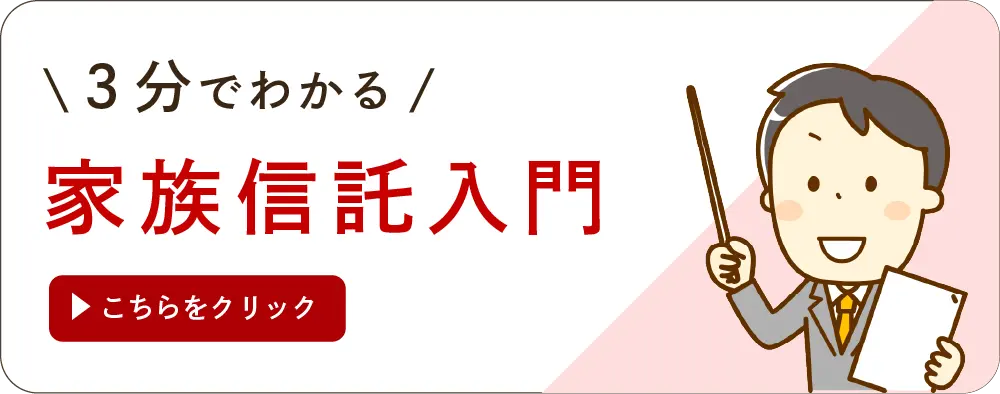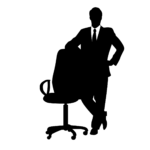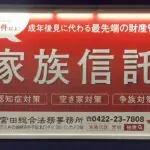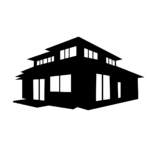家族信託
「家族信託」を既に検討されている方へ
弊所は、まだ「家族信託」「民事信託」という言葉が一般の方はもちろん、
専門職の間にもほとんど知られていない頃から、その設計コンサルティングサービスを提供しておりました。
弊所は、いわば家族信託の“老舗”で、日本屈指の組成実績を誇ります。
また、家族信託とは切っても切れない“家族会議”への同席・立会いも数えきれず、
修羅場や困難事例も含め、様々な経験を踏まえた対応を得意としております。
実際にご相談いただけましたら、家族信託を手掛ける他の専門職との違いにお気付きいただけるのではないかと自負しております。
家族信託のことでご不明な点・ご不安な点・お困りな点等ございましたら、どうぞお気軽にご連絡下さいませ。
「家族信託」をまだよく知らない方へ
家族信託の仕組みやメリットがよく分からない、成年後見制度との違い・使い分けがよく分からない。
そういう方でも、大歓迎です!
むしろ、今ご家族が抱えている課題・悩み、これから先の財産管理・資産承継についてのご希望・ご要望を
お聞かせいただくことから始めさせていただいておりますので、「家族信託」の事前勉強は一切不要です。
家族信託の検討が本当に必要ということになれば、弊所から必要なタイミングで分かりやすくご説明いたしますので、
まずは、お気軽にご相談下さいませ。