-

-
家族信託・福祉型信託も信託業法の適用を受けますか?
家族信託・福祉型信託は、原則として信託業法の適用を受けません。 信託業法の適用を受けるのは、その内容が「信託の引受けを行う営業」に該当する場合です。 つまり、『受託者が不特定多数を相手に反復・継続して ...
-

-
家族信託や相続対策の検討における「家族会議」の重要性
『家族信託』という仕組みは、遺言の代用機能として直近の遺産の受取人(1次相続人)の指定だけでなく、その次の相続(2次相続)以降の財産の承継者も指定できる画期的な手法です。この機能を上手に活用することで ...
-

-
家族信託を実行する際の注意点・リスク・デメリットとは
『家族信託・民事信託を実行することのリスクやデメリットはありますか?』というご質問をよく頂きますが、結論として、きちんとした設計をすることができれば、家族信託・民事信託のリスクやデメリットはほぼ無いと ...
-

-
『家族信託』と生命保険の共通点・相違点
◆家族信託と生命保険の共通点◆ 生命保険(本稿では、「死亡保険金」を想定。)は、様々な目的で活用されています。 その活用の目的の代表的なものは、下記のようなものが挙げられます。 ≪相続税対策としての保 ...
-

-
平成28年10月1日より商業登記に「株主リスト」が必要になります!
≪企業の総務部・法務部の方必見!≫ =株主名簿の管理できてますか?= ~商業登記手続きに「株主リスト」が必要になります~ 商業登記規則等の改正により、平成28年10月1日以降の株式会社等の登記の申請に ...
-

-
任意団体の法人化の大まかな流れ
同窓会・管理組合等の任意団体を法人化して一般社団法人にする際の大まかな流れは、下記のとおりです。 (1)設立時社員を確定(2人以上) ↓ (2)定款の作成 ※ ↓ (3)公証人による定款の認証 ↓ ( ...
-

-
任意整理のメリット・デメリット
◆メリット◆ ・司法書士又は弁護士の法律家が債務整理手続の正式依頼を受任した旨(これを“受任通知”といいます)を各債権者に送付した段階で、本人に対する取立行為が止みます(債務整理手続き全般に共通するメ ...
-

-
生命保険金を争族対策に活用する正しいやり方
将来の相続発生の際に、自宅不動産や自社株式等(事業資産)を複数の相続人に分散させずに特定の後継者に承継させ、残りの資産(預貯金や別荘等)を他の相続人に承継させたいというご相談は多いです。 この場合、ほ ...
-

-
家族信託を活用すれば認知症後も暦年贈与可能?
『民事信託・家族信託の仕組みを活用することにより、相続税対策としての暦年贈与を、贈与者が認知症等で判断応力喪失後も、受託者主導で着実に実行できるか?』 というご質問をよく頂きますので、この点につきご説 ...
-

-
家族信託においても“倒産隔離機能”で財産を守れるか
「倒産隔離機能」は、信託法という法律を学ぶ方にっては、非常に重要ですが、民事信託・家族信託の実務においては、あまり重要度は高くない機能ですし、そもそも多くの方がこの説明に対して誤解をしているようです。 ...
-

-
農地を家族信託契約の信託財産とする際のポイント 【2022年最新版】
登記簿上の農地(具体的には、地目が「田」や「畑」になっている土地)については、「農地法」という法律の適用を受け、農業委員会の許可又は届出(市街化調整区域については許可、市街化地域については届出。以下、 ...
-

-
平成28年度税制改正による「相続空き家控除」について
昨今の社会問題となっている「空き家問題」ですが、その大きな要因が、相続発生によって、その主を失い、引き継ぐ主もいない、従って管理も行き届かない…という事態です。 これを防ぐ政策として、平成28年度税制 ...
-

-
家族信託で株式を信託する場合の注意点
中小企業のオーナー社長や創業者一族が、相続・事業承継対策として、あるいは大株主の判断能力低下による株主総会の開催不能(経営判断機能の凍結)のリスクに対する事前策として、未上場株式を信託財産として家族信 ...
-
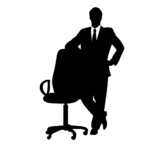
-
相続の限定承認申述手続
相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択できます。 (1)相続人が被相続人のプラスの資産はもちろん借金等の義務もすべて受け継ぐ[単純承認] (2)相続人が被相続人の権利や義務を一切受 ...
-

-
相続放棄の必要書類 ≪家庭裁判所への申述手続き≫
相続放棄とは、債務超過の相続財産を承継したくない場合や遺産を承継することを拒否したい相続人の意思を尊重する制度であり、相続の開始によりその相続人に帰属すべき一切の権利義務を家庭裁判所の手続を通して確定 ...
-

-
自筆の遺言書を発見した場合 ≪遺言書検認手続≫
相続開始後、自筆の遺言書を発見した場合には、遺言書を勝手に開封することは許されておりません。 自筆の遺言書は、家庭裁判所にて「遺言書検認手続」を受け、家庭裁判所で相続人立会いのもと、開封することが必要 ...
-

-
遺産分割協議書作成の手引き
被相続人が遺言書で相続財産をどのように承継させるかを決めていなかったり、遺言書に記載の無い相続財産が存在する場合、当該遺産のすべては、相続人が概念的に法定相続分で相続したことになります。 従いまして、 ...
-

-
生命保険を活用した“争族対策”・“相続税対策”
生命保険を活用した争族対策・相続税対策については、大きく分けて下記の3つの要素があります。 (1)争族・遺産分割対策 (2)相続税対策その1:納税資金対策 (3)相続税対策その2:相続税対象財産の圧縮 ...
-

-
家族信託(民事信託)と商事信託の比較
①信託できる財産の範囲の違い 【家族信託】 不動産・現金・未上場株式が中心です。証券会社・信託銀行の金融実務が家族信託に対応できていないので、 上場株式・国債・投資信託等の有価証券類を信託財産に入れる ...
-

-
空き家対策特別措置法と家族信託
『空家等対策の推進に関する特別措置法』、いわゆる「空き家対策特別措置法」が先月(2015年5月26日)、 全面施行されました。 倒壊や放火のリスク、不法投棄、不法侵入者の存在、景観を損ねる等の理由で、 ...




