-

-
売掛債権の上手な回収作戦 5つのPoint!
Point 1 取引相手の信用力・支払余力・所有資産を事前に把握! 売掛金が焦げ付いたときに一番重要なことは、法的手段を行使しても最終的に売掛金を回収できる資産を相手が持っているかどうかに尽きます。取 ...
-

-
NPO法人の活動例
現在すでに活動しているNPO法人をいくつか紹介したいと思います。 簡単なかたちではありますが、これからNPO法人を設立しようと考えている方々の参考として少しでもお役に立てれば幸いです。 1. 「保健、 ...
-

-
NPOに吹く追い風
2007/7/2 NPO, パブリックマーケット, 民間開放
最近になってNPOが注目を浴び始めてきている背景としては、さまざまな要素が考えられますが、特に重要な要素と考えられるのは、次の点です。 1.政府の官製市場の外部化推進 政府は、民間でできることは、なる ...
-

-
公益認定の基準の内容
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(いわゆる“公益法人認定法”)の 第5条に規定された公益認定の基準は、下記のとおりになります。 ? 公益目的事業を行うことを主たる目的とすること ? ...
-

-
公益目的事業一覧
公益法人の公益認定基準を満たすための事業は下記のとおりです。 1.学芸及び科学技術の振興を目的とする事業 2.文化及び芸術の振興を目的とする事業 3.障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは ...
-
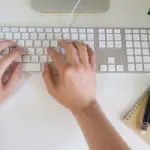
-
一般社団法人・一般財団法人の制度の概要
一般社団法人は、2名以上の社員によって設立できることとし、設立時の財産保有規制は設けないこととするほか、社員総会及び理事を必置とし、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を設置できることとして ...
-

-
特定調停とは
『特定調停』とは、簡易裁判所に申し立てをして調停委員が債権者と債務者との間に入り、残債務額の確認や今後の返済方法などを話合い、解決を図る手続です。 ただし、交渉がまとまった場合、調停調書には判決と同じ ...
-

-
民事再生手続きと自己破産手続きの違い
自己破産(+免責手続き)とは、裁判所で財産もなく支払不能であることを認めてもらい、すべての借金を裁判所の命令で強制的に免除してもらう手続です。 【自己破産】 破産宣告及び免責決定を受けるためには、一定 ...
-

-
任意整理手続きと民事再生手続きの違い
「任意整理」とは、裁判外で、弁護士や司法書士が各債権者と交渉して、利息制限法に基づいて過去の払い過ぎた利息を計算しなおして、これを元本の支払いに充当し借金を減額してもらい、その金額に基本的には利息をつ ...
-

-
民事再生手続きのメリット・デメリット
<メリット> 1.借金の減額 裁判所の関与のもと、原則3年(最長5年)の分割払いで債務全額を返済するような計画が立てられますので、元本が大幅カット(最高で負債の総額が5分の1まで圧縮可能)されます。 ...
-

-
任意整理の必要書類
裁判所を介する手続ではないので、絶対的な必要書類というものはありませんが、下記のものがあれば、任意整理へ向けた手続が非常にスムーズに運びます。 また、利息制限法に利息を引き直すと、完済していたり、利息 ...
-

-
任意整理とは
『任意整理』とは、借金の整理(債務整理)方法のひとつで、裁判手続を経ずに、司法書士・弁護士が代理人となって(介入して)、債務者本人の代わりに各債権者と個別に交渉をし、残債務額の確認や返済総額の減額交渉 ...
-

-
個人再生手続きとは
個人民事再生手続とは、「一定の要件を満たす場合、裁判所の関与のもと住宅などの財産を手放さずに借金の一部を免除してもらい、圧縮後の債務残額を3年程度(最長5年)で分割して返済ことで債務を整理するという債 ...
-

-
中小企業の定時株主総会開催までのスケジュール
2007/4/6 定時株主総会, 株主総会スケジュール
定時株主総会開催までのタイムスケジュールは、取締役会設置会社であるかどうか、監査役設置会社であるかどうか、会計監査人設置会社であるか等、株式会社の機関設計の違いによって異なります。 今回は、その中でも ...
-

-
合同会社(日本版LLC)
2006年4月施行の新・会社法により全く新しい組織が誕生しました。 その名も『合同会社』。米国で普及しているLLC(リミテッド・ライアビリティ・カンパニー)の日本版であります。 「1円起業」で話題を呼 ...
-

-
合同会社(日本版LLC)
2006年4月施行の新・会社法により全く新しい組織が誕生しました。 その名も『合同会社』。米国で普及しているLLC(リミテッド・ライアビリティ・カンパニー)の日本版であります。 「1円起業」で話題を呼 ...
-

-
有限責任事業組合(日本版LLP) その2 ≪仕組み≫
2007/3/30 LLP
(1)組合員 LLPの組合員になるための特別な要件はなく、個人又は法人は1円以上の出資をすれば組合員になることができます(国内非居住者や外国法人も可能)。 ただし、民法組合がLLPの組合員になることは ...
-

-
有限責任事業組合(日本版LLP) その1 ≪特徴≫
2007/3/30 LLP
2005年8月1日より全く新しい組織が誕生しました。 その名も『有限責任事業組合』。 米国で普及しているLLP(リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ)の日本版です。 事業者や専門家が連携して行 ...
-

-
有限責任事業組合(日本版LLP)
2005年8月1日より全く新しい組織が誕生しました。 その名も『有限責任事業組合』。 米国で普及しているLLP(リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ)の日本版である。 事業者や専門家が連携して ...
-

-
遺言執行者の選任申立手続
遺言執行者がいないとき、又は遺言執行者が亡くなったときは、利害関係人(相続人、相続債権者、受遺者など)が、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てることができます(民法第1010条)。 遺言書の中で遺言執 ...




