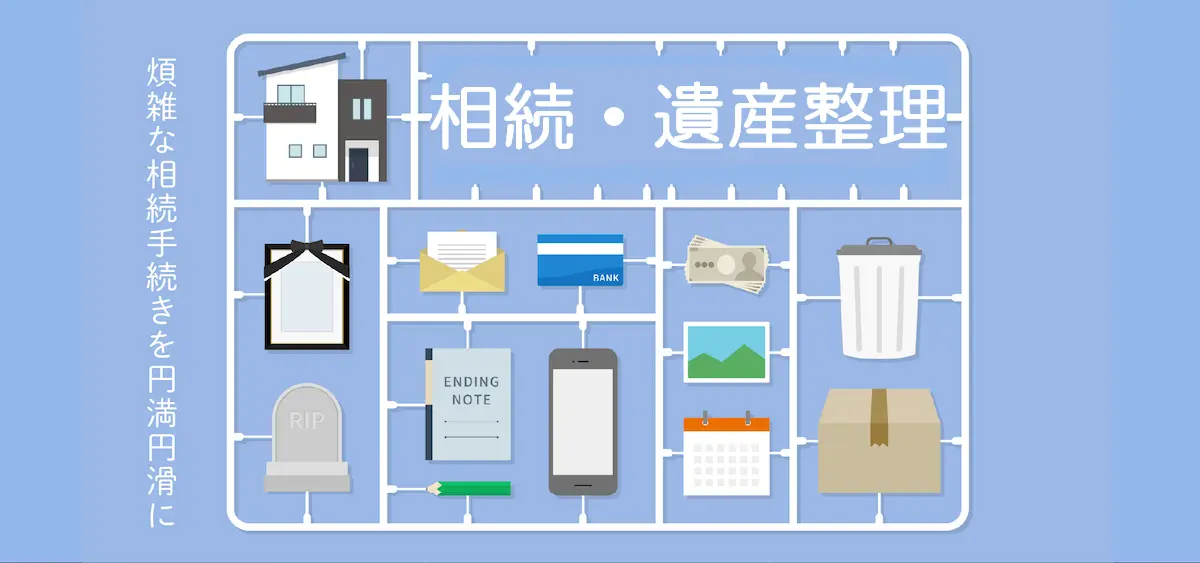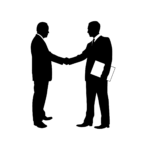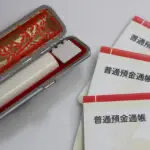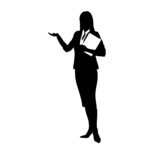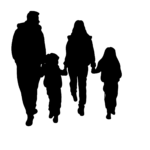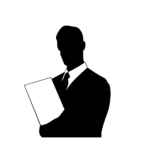相続・遺産整理
相続・遺産整理・遺産相続・遺産分割に関する手続は、複雑かつ繊細な問題です。
方向性を誤ると、権利を喪失したり、“争族”に発展したりと、思わぬ事態が巻き起こります・・・。
まずは、遺産相続・遺産整理・遺言執行を数多く手がける弊所までお気軽にご相談下さい。
弊所の≪無料法律相談≫をご利用頂き、今後の正しい方向性を見定めることから始めましょう!
お時間ある方は、こちらもお読みください・・・
相続に関する手続は、法定相続人が直系卑属(子供)かそれとも兄弟か、遺言書があるか、遺言執行者がいるか、相続すべき財産があらかじめ把握できているか、法定相続人間で遺産分割の大まかな合意は容易に得られそうか…等様々な要因にもよりますが、想像以上に複雑で手間がかかるものです。

預貯金口座の名義書換一つをとってみても、金融機関ごとに所定の届出用紙があり、必要書類も異なりますので、平日の日中に何度も各窓口に足を運ぶ必要が出てきます。
また、必要書類(戸籍謄本等)を市区町村役場等で集めなければなりませんので、本籍地が遠方だったりすると、それだけで相当な手間と負担を強いられます。特に平日働いている方やご高齢の方には、相当気の重い作業だと思います。
このような方に代わって、当事務所では、これから何をどういう手順ですべきか、最終的にどういった作業・手続が必要か、その為の必要書類は何か等、分かりやすくご説明の上、相続手続・遺産整理のプロとして素早く対応させて頂きます。
あるいは、全く別のケースとして、遺言書はあるが遺言内容に不満があり、遺言内容の実現に向けて他の相続人の協力が得られない場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立をする事をお勧めします。当事務所が執行者に就任することで、相続人に代わって遺言内容の実現の手続を遂行することができます。
相続・遺産整理・遺産分割・遺言執行に関する諸問題については、お気軽に当事務所にお問い合せ下さいませ。
微妙な相続人関係での遺産整理に有効!
相続人全員の間で必ずしも良好な関係が築かれているとは限りません。
この場合、最も大切なことは相続人間での無用な対立を避けることです。
遺産整理で対立を避けるには、“初動”が肝心です。
遺産整理では話の切り出し方や進め方を間違うとドロドロの相続争いに発展する可能性があります。
しかし、きちんとした話し合いのきっかけや話し合いの場さえあれば、話がまとまるケースは実は多いです。
故人も含め、誰も争いを望んでない以上、“話せばわかる”という場合は意外と多いのです。
にもかかわらず、“相続問題は弁護士だろう”と思い込み、すぐに弁護士に相談される方も多いです。
そうすると、大抵の場合、弁護士から相手方に手紙が行きます。

果たしてこれが、得策でしょうか?
初動としてとるべきベストな手段なのでしょうか?
あなたが弁護士から手紙を受け取った場合を想像してみてください。
ほとんどの方は、慌てて弁護士等の法律家に相談に行くでしょう。
「相手方に弁護士がついた以上、素人の自分では手に負えない。費用はかさむが、こちらも弁護人をたてよう。」
こうなると思います。
遺産整理において弁護士を立てるということは、通常、“宣戦布告”に近い強烈な印象を相手方に与えてしまい、態度を硬化させる可能性がかなり高まります。
当事務所では、ご相談・ご依頼をいただいた場合、まずはご本人からのご連絡(お手紙)をお勧めしています。もちろん、手紙の文面は当方で全面的に推敲します。
「自分からの手紙を出すのはちょっと・・・」という方や本人からの手紙にリアクションが薄い場合等には、当事務所からご挨拶のお手紙を出します。
ただし、我々は依頼者本人の代理人として手紙を出すのではなく、あくまで穏便な解決を図る中立的な第三者の立場からアプローチをします。
本来の意図は、相手を打ち負かすことではなく、話し合いの場を設け、喧嘩することなく話を穏便にまとめることです。
そのために我々は全力を注いでそのお手伝いをいたします。
確かに当事者に代わって代理人弁護士が立つことで話がスムーズにまとまることもあるでしょう。
しかし最初から、高額な費用を払って弁護士を立てまで、話を進めなければならないのでしょうか?
まずは、“争う意はないこと” “できるだけ早く双方納得のできる解決策を探りたいこと”を相手方に伝えることから始めませんか?
そこはもはや法律論の問題ではありません。
感情的な要素が大きく深く影響している問題だからこそ、法律をかざすことが必ずしも解決への近道とは限りません。
あくまで、遺恨を残さない解決を目指します。
弁護士に依頼することは、いつでもできます。
裁判所に調停を申し立てることも、いつでも可能です。
でも、その前に試みてみませんか?
みんなが穏便に話し合いのテーブルにつくきっかけを、方法を。
我々はそんなお手伝いをしています。
まずはお気軽にご相談に来てみてください。
※交渉が決裂した場合は、裁判所へ調停申立てという選択肢もありますし、弁護士をご紹介して事件を引き継ぐことも可能です。
相続・遺産整理におけるお手続きの内容
相続・遺産整理手続きは、ご相続人全員の協力を得る必要があり、かつ煩雑で時間のかかる作業を伴います。
ご相続人様のご負担を少しでも軽減するため、弊所では、相続手続きの工程ごとにお手伝いをするメニューを取り揃えております。
1. 法定相続人の調査(法定相続人の特定及び居住地の捜索)、相続人・親族へのご連絡
- 戸籍の代理収集&法定相続情報一覧図作成
- 戸籍附票の代理取得(相続人の住所調査)
2. 相続人・親族へのご連絡
- 法定相続人に遺産整理手続きへのご協力のお願い通知
- お電話でのご挨拶&ご説明&ご協力への了承
3. 相続財産の調査・財産目録の作成
- 預貯金口座・証券口座の有無確認
- 残高証明書・取引履歴の取得
- 不動産の調査(名寄帳・登記事項証明書・公図・測量図等の取得)
↓↓↓
遺産の全貌を把握 ⇒ 財産目録の作成 - 相続税申告義務の有無を確認
⇒ 必要に応じて税理士さんのご紹介も
遺産分割協議書の作成・調印サポート
- 遺産分割案のご提案&遺産分割協議の調整
- 分割協議書の作成&相続人全員の調印サポート
金融資産の相続手続き・分配・不動産の相続登記
- 預貯金の解約払戻
- 債務及び諸費用の支払い
- 有価証券の名義変更
- 不動産の相続登記・換価処分
- 配当計算書の作成
⇒相続人全員の了解を得られたら遺産の分配
遺産相続・遺産整理・遺産分割・遺言執行の流れ
(相続税の申告義務があるか・納税額が発生するかを判断)
(相続税の申告義務がある場合のみ)
遺産整理業務の報酬基準表(消費税込)
1. 遺産整理業務に関する報酬は下記のとおりとする。但し、遺産の受取人が複数いる場合は、各人ごとに算出する。
※ 報酬算定の基礎となる財産の価格は、遺産整理業務対象財産の相続開始時点の相続税評価額
(但し、不動産については、固定資産評価額を原則とする)とし、負債等の控除前のプラスの財産の総額となります。
| 渡時の財産の価格について | 報酬額(税込) |
| 200万円以下 | 応相談 |
| 200万円超― 500万円 | 33万円 |
| 500万円超― 5,000万円 | (1.2 % +25万円 )+ 10% |
| 5,000万円超― 1億円 | (1.0 % +35万円 )+ 10% |
| 1億円超― 3億円 | (0.7 % +65万円)+ 10% |
| 3億円超 | (0.4 % + 155万円)+ 10% |
(令和6年1月1日改定)
※ 相続人間の利害調整により、法定相続分に相当する価額よりも多くの遺産を取得することができた受取人に対しては、当該増加分の10%の追加報酬を頂戴します。
※ 対象となる預貯金口座数が金融機関単位で8個以上ある場合には、別途追加報酬を頂きます。
2. 契約書第3条第14号の規定に基づき遺産整理対象財産の処分をしたときは、前項のほか売却代金の3%以内(消費税別)の報酬を受領することができる。
3. 本件業務の処理のため半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日(3.5時間以内)あたり金39,600円(税込)、1日(3.5時間超6時間以内)あたり金72,600円(税込)を受領することができる。
4. 本件業務に必要な書類を代理で取得するときは、下記の報酬を頂戴します。※ 郵送料・交通費等は別途
| 種別 | 報酬額(税込) | 備考 |
| 戸籍・除籍・改製原戸籍謄本 | 3,300円/通 | 実費は別途 |
| 住民票・住民票除票・戸籍附票 | 3,300円/通 | 実費は別途 |
| 外国人登録原票 | 3,850円/通 | |
| 固定資産評価証明書 | 1,980円/通 | 但し、1ヶ所につき最大3,960円、実費は別途 |
| 名寄帳写し | 3,300円/通 | 実費は別途 |
| 不動産情報のネット閲覧 | 880円/通 | 実費は、1通 332円 |
| 全部事項証明書(不動産謄本) | 1,100円/通 | 実費は、1通 480円又は600円 |
| 公図・地積測量図・建物図面 | 1,100円/通 | 実費は、1通 430円又は450円 |
★ 以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。
ア) 不動産の登記手続に関する登録免許税、謄本印紙代、郵送料等の実費
イ) 相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬及び実費
遺言執行業務の報酬基準表
1.遺言執行業務に関する報酬は、下記のとおりとなります。
※ 報酬算定の基礎となる財産の価格は、遺言執行業務対象財産の相続開始時点の相続税評価額
(但し、不動産については、固定資産評価額を原則とします)とし、負債等の控除前のプラスの財産の総額となります。
| 対象となるプラスの資産総額について | 報酬額(税込) | 備考 |
| ~3,000万円以下 | (2.0 % + 30万円)+ 10% | 約44万円~99万円 ※最低44万円 |
| 3,000万円超~3億円以下 | (1.0 % + 60万円)+ 10% | 約99万円~396万円 |
| 3億円超 | (0.5% + 210万円)+ 10% | 約396万円~ |
(令和6年1月1日改定)
※ 遺言による相続又は遺贈を原因とする不動産の所有権移転登記手続き報酬については、本報酬に含まれますが、不動産の登記申請件数が4件以上ある場合には、4件目以降申請1件につき金44,000円(税込)の追加報酬を頂戴します。
※ 対象となる預貯金口座数が金融機関単位で8個以上ある場合には、金融機関1個につき金55,000円(税込)の追加報酬を頂戴します。
2. 遺言に基づき不動産を換価処分をしたときは、前項のほか売却代金の3%以内(消費税別)の報酬を受領することができるものとします。
3. 本件業務の処理のためとき半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日(3.5時間以内) あたり金39,600円(税込)、1日(3.5時間超6時間以内)あたり金72,600円(税込)を受領 することができるものとします。
4. 本件業務に必要な書類を代理で取得するときは、下記の報酬を頂戴します。※ 郵送料・交通費等は別途
| 種別 | 報酬額(税込) | 備考 |
| 戸籍・除籍・改製原戸籍謄本 | 3,300円/通 | 実費は別途 |
| 住民票・住民票除票・戸籍附票 | 3,300円/通 | 実費は別途 |
| 外国人登録原票 | 3,850円/通 | |
| 固定資産評価証明書 | 1,980円/通 | 但し、1ヶ所につき最大3,960円、実費は別途 |
| 名寄帳写し | 3,300円/通 | 実費は別途 |
| 不動産情報のネット閲覧 | 880円/通 | 実費は、1通 332円 |
| 全部事項証明書(不動産謄本) | 1,100円/通 | 実費は、1通 480円又は600円 |
| 公図・地積測量図・建物図面 | 1,100円/通 | 実費は、1通 430円又は450円 |
★ 以下の諸費用は、別途、各ご相続人・受遺者様のご負担になります。
ア)不動産の登記手続に関する登録免許税、謄本印紙代、郵送料等の実費
イ)相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬及び実費
遺産相続・遺産整理・遺産分割・遺言執行に関する無料法律相談
無料法律相談または電話(0422-23-7808)まで是非ご相談下さい。
営業時間 : 平日8:30から19:00まで (ご予約により、時間外のご相談も可能です)
※土日祝日は、事前予約にてご相談を承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。